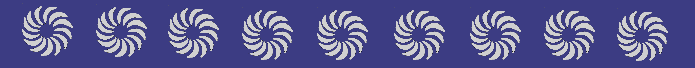2日目 5月18日(日)
(注) 本会HPの規定により未成年者の名前はイニシャルで表記し、写真は処理をしています。
| 今日も天気は大丈夫。気温も少し昨日よりは低いようです。二日目の奉納に向けて、みんなで頑張ります。 |

| 部員が公民館に集まってきました。稚児たちは衣装を整えます。 |

 
| 舞で使う道具や必要なものを台車やリアカーに詰め込みます。もちろんエネルギーの元も(笑) |

昨年、新調した台車には、太鼓やバチ・笛の予備、稚児の房・水差しなど舞に必要なものを運びます。水差しは、笛を濡らすために使います。
笛は吹いているときに、口が渇いてきて音が出にくくなります。そのため演奏中に笛の口元を水につけて吹き始めると口の乾きがなくなります。笛の演奏者の足下に置いています。
この水差しは竹からつくった手作りなのです。竹を形に切って人工漆(カシュー)を塗ります。
そして、三階菱の家紋をつけて完成です。今使っているもの多くは10年前に作ったものなので、現在では、塗り直したり、修理したりして使っています。 |
  
| 竹の切り出し → 水差しの形に切って整えます → カシュー(人工漆)塗り |

完成!

| 時間になりました。地元でのお立ちの舞に出発です。隊列を組んで出発です。 |


例年、2日目のお立ちは上伊田駅で行っていました。この場所は決まりではなく、地域からの要望があれば変更が可能でした。
今回、デイサービスの「すずか」様から場所の提供があり変更となりました。 |



| 子どもたちは、広い敷地より、水たまりが気になっていますね。 |

笛部の姉様方

| 縁の下で私たちをさせてくださっている「女性の会」の姉様方。 |

| 地域の方々が見に来てくださっている中で、地元でのお立ちの舞です。 |




初めての場所でしたが、足下もきれいに整備され、獅子や稚児たも舞いやすかったようです。
地元の方々に良い舞を披露できました。 |


稚児の背につけられている五色の布の先につけられている鈴には意味があります。
神社にはお参りをするときに鈴を鳴らします。この行為は、神様をお招きし、場の邪気を払い、神様を敬うために用いられると言われています。さらに、鈴の音色には浄化作用があるとされ、神様が好むとも言われています。本会の稚児には神さまが憑依すると言われています。神さまをお招きするためにこれらの鈴は大切なものとなります。 |

| 地元でのお立ちの舞が終わり、御旅所へ向かいます。2日目は地区内を大回りするので、低学年の稚児たちとは、少しの間、お別れです。 |


御旅所へ向かう途中、今年も炭坑節で有名な日本煙突と伊田立坑櫓が見えて来ました。
「炭坑節発祥の地 田川」を代表する建物です。 |

| 小倉の小笠原藩の穀倉地帯である田川には、農地がたくさんあります。私たちの道中の周りにも麦が植えられています。福岡県の麦の生産は、北海道に次いで全国2位とのこと。そういえばラーメン屋さんに行くと「福岡県産ラー麦使用」とよく書かれていますね。 |

| 公民館からすぐ下の道路に到着しました。ここで先ほどお別れした低学年の稚児たちと合流し、いっしょに歩いて御旅所に向かいます。 |

| 御旅所に近づくと、露店も多くなり賑やかな雰囲気になります。 |

御旅所に到着。11台の山笠により華やかな光景が広がります

| 到着後、風治八幡宮の御神輿の前に獅子頭を据えます。 |

| 白鳥神社の神輿の前にも獅子頭が据えられています。住民の方の家に保管されていたそうです。 |

川渡り青年友志は今年で30周年を迎え記念写真
おめでとうございます!

広場で炭坑節
その後、御神輿が神社に戻る「宮入り」が始まります。

| 神輿の出立を前に、獅子楽を奉納し、神輿の渡御を脅かす悪霊を威圧して道を清めます。 |

獅子の舞には、「悪霊退散」の役目と共に「五穀豊穣」・「子孫繁栄」の意味もあります。
特に、稚児は240年前の「天明の大飢饉の後に稚児舞が奉納された」とあります。稚児たちに神さまが憑依して、五穀豊穣の願いが込められているのです。そのため稚児舞には農作業と思われる所作が見られます。
五穀豊穣の五穀とは?
「米・麦・粟(アワ)・大豆・大豆」もしくは「米・麦・粟(アワ)・稗(ヒエ)・豆」で古事記や日本書紀で違ってるのかな? |


| 鮮やかな山笠に稚児たちの衣装が重なるとさらに鮮やかになりますね。 |


| 稚児たちの衣装の背には五色の布が添えられています。この五色は、五行思想を表したもので、「赤・青・黄・白・黒」が基本となりますが、本会では、「白を桃、黒を紫」として使用しています。 |



| 風治八幡宮では、食事をして、長い休憩時間になります。その間、河川敷では川渡り神事が行われています。私たちは、納めの舞まで、のんびりとします。 |


御旅所から出発する山笠


川渡り神事

 
子どもたちものんびりはしゃいでいました


| 神輿が、田川伊田駅前にやってきました。そろそろ神社にお戻りになる時間が近づいてきました。部員たちもこの頃には神社の境内に待機をしています。 |

御神輿が神社に戻ってきました
境内で何度か回ります。

御神輿は、時より3回ほど大きく持ち上げます。
神さまが御神輿に乗って渡御すれば神さまの力を振りまいて人々の災いを避けるはたらきがあります。大きく揺さぶることで、さらに神様の力を高めて豊作を願うといわれているのです。 |


| 稚児たちの笑顔は、神輿の担ぎ手の皆さんの疲れを癒やしてくれることでしょう。 |

| 稚児の俵担ぎの所作。令和の大飢饉を解消して欲しいですね。 |


今年の神幸祭の奉納は終了しました。神輿のみなさん、来年再会しましょう!
御神輿の前で一本締め!! |
御礼

(風治八幡宮 社殿前にて)
| 今年も神幸祭での奉納を終えることができました。無事に終えることができたのは、実技者以外の力が大きな要因になります。写真内の隣組組長さんをはじめ、女性の会、写真には写っていませんが、影で支えてくださった協力者のみなさま、地域の住民のみなさま、さらに奉納や隊列の運行に際してご配慮いただいた神社関係・神輿・山笠のみなさま、「まつりinたがわ」のみなさま ありがとうございました。 |
おわり
|